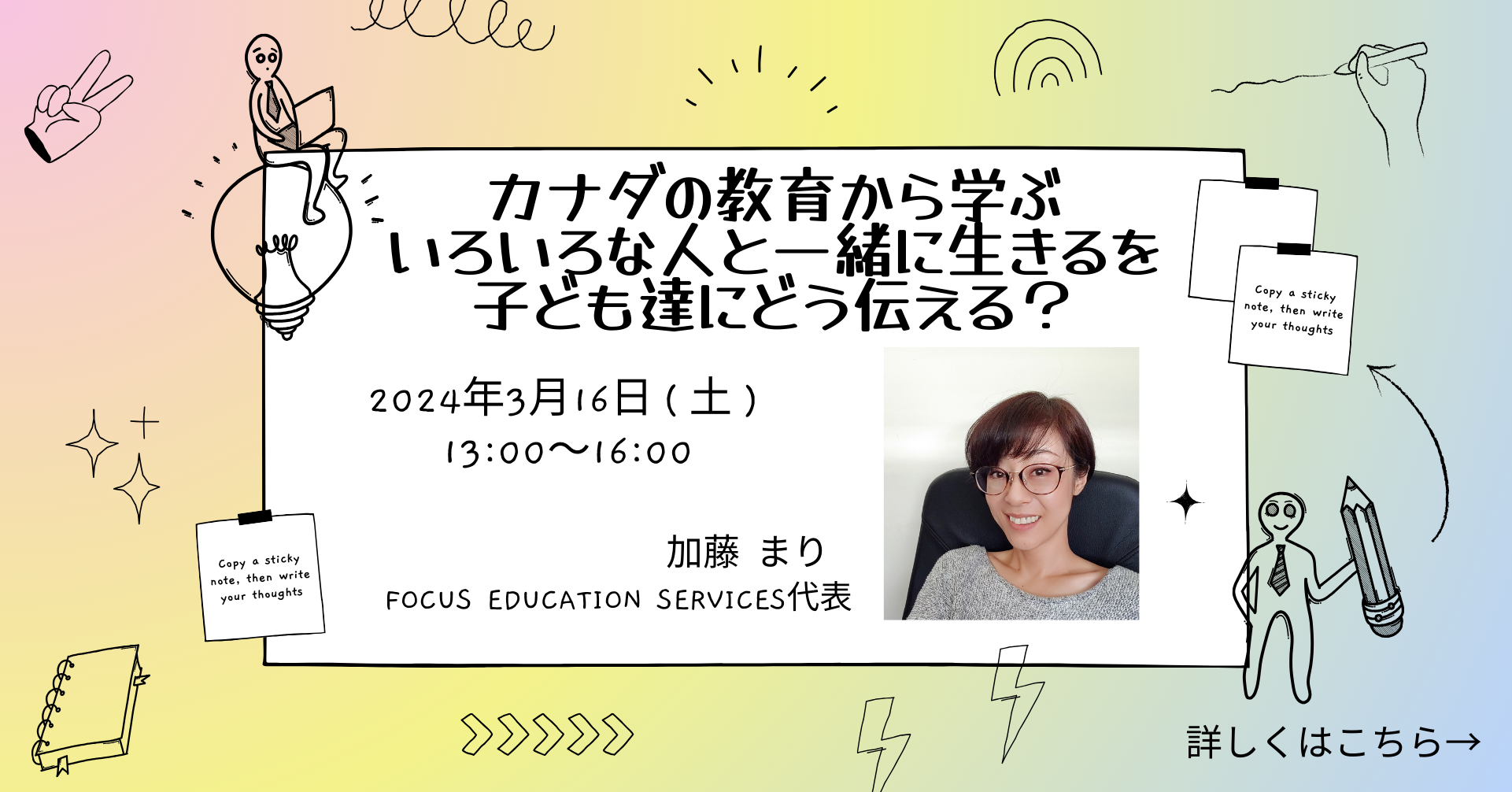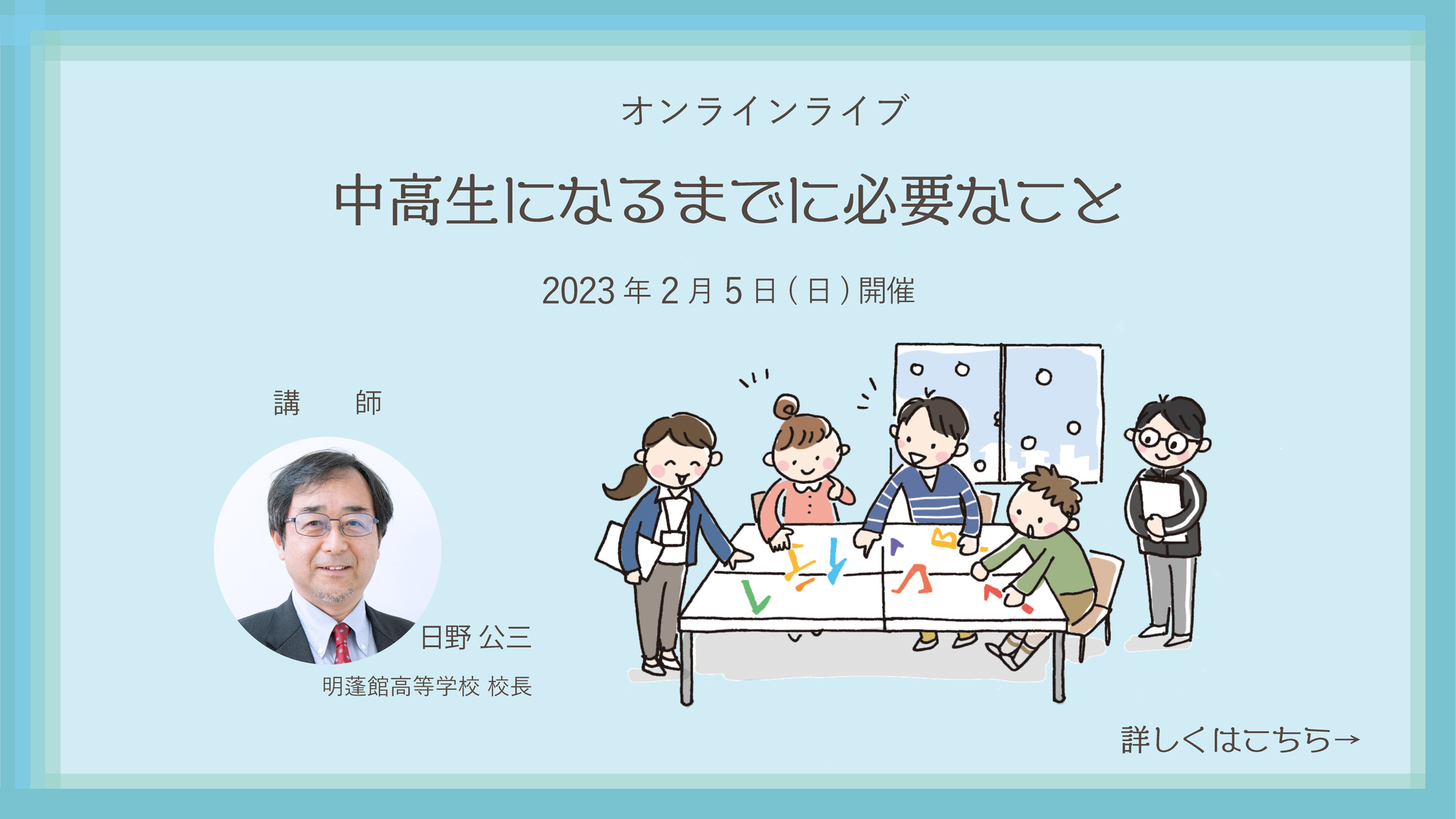終了した講座
NPO法人日本インクルーシブ教育研究所では、毎年、学習・発達支援員の養成講座を開講し、教室での実践に役立つ知識とスキルを提供しています。しかし、多くを学び実践を積んだとしても、多様な子どもたちに寄り添い続けることはそう簡単なことではありません。
そこで、ライセンス取得者や過去に養成講座を受講された方を対象に、フォローアップ研修を毎年開催しています。本研修では、実践を深めるための学びを提供し、支援の質をさらに向上させることを目的としています。
今回の研修では、オランダ在住の三島菜央さんを講師に迎え、「自分らしくいることを大切にするオランダの教育」をテーマにお話しいただきます。一人ひとりが尊重されるオランダの教育から、学習や発達の支援のヒントを学び、日々の実践に活かしていきましょう。
自閉スペクトラム症の人達に伝えるためには、まずは私達が自閉スペクトラム症の人達への特性理解が必要です。そして、自閉スペクトラム症の人達の特性に合わせた文章が書けるようになると伝わるようになります。本講座では、こちら側からのコミュニケーションとして自閉スペクトラム症の人達が「心穏やかに、前向きに、気持ちよく」理解できる文章の書き方を学びます。
カナダの教育から、異文化や多様性を受け入れるためにはどういった視点や発想が必要なのかを学びます。 今回、初めて里山で開くこのワークショップでは、異なる文化からの考え方や視点を学び、自身の中にある思い込みに気づく体験をします。カナダの教育事例を基に、社会とのつながりを考え、異文化への理解を深め、普通って何なのだろう?と考えたり、一緒に生きることを大切にした社会はどんな風に成熟していくのかを考えていきます。東広島の美しい自然の中で、癒しと学びの時間を私たちと一緒に楽しみませんか?
NPO法人日本インクルーシブ教育研究所では毎年、教室で活躍する学習・発達支援員を養成しています。一度、学習・発達支援員養成講座を受けただけでは多様な子ども達に合わせて適切なサポートをし続けることは難しいものです。そのため、ライセンス取得者だけでなく学習・発達支援員養成講座を受講したことのある方はどなたでも受講できるようフォローアップ研修も毎年開催しています。今回は講師にインクルーシブな社会がすすんでいるデンマーク在住のピーダーセン海老原さやか先生をお招きし、デンマークの特別支援学校で大切にしていることを学びます。
自閉スペクトラム症の人達に伝えるためには、まずは私達が自閉スペクトラム症の人達への特性理解が必要です。そして、自閉スペクトラム症の人達の特性に合わせた文章が書けるようになると伝わるようになります。本講座では、こちら側からのコミュニケーションとして自閉スペクトラム症の人達が「心穏やかに、前向きに、気持ちよく」理解できる文章の書き方を学びます。
広島県央の湖畔ホテルで英語の読み書きが楽しくなるイギリスの指導法を紹介します。山里のリゾートならではの森林浴や満点の星空を満喫しながら、多感覚を使って学ぶ英語を体験してみませんか?イギリス在住の山下桂世子先生が広島までお越しくださいます。子ども達が楽しみながら英語の読み書きを学ぶことができる方法です。
7月31日と8月1日の2日間でジョリーフォニックスのお泊まり研修を開催します。2日間で42音と同音異綴り、ひっかけ単語を紹介して、読み書きにはスモールステップが必要であることを学びます。そして、読み書きに困難のある子どもたち、暗記が苦手な子どもたちにどんな指導をしたらいいのかを具体的に一緒に考えていきます。まずはオンラインライブ説明会を開きますので、ぜひご参加ください。
7月31日と8月1日の2日間でジョリーフォニックスのお泊まり研修を開催します。2日間で42音と同音異綴り、ひっかけ単語を紹介して、読み書きにはスモールステップが必要であることを学びます。そして、読み書きに困難のある子どもたち、暗記が苦手な子どもたちにどんな指導をしたらいいのかを具体的に一緒に考えていきます。まずはオンラインライブ説明会を開きますので、ぜひご参加ください。
自閉スペクトラム症の人達が理解しやすい書いて伝える方法を学ぶソーシャルライティング講座が6月20日から始まります。どうすれば自閉スペクトラム症の子ども達とうまく関われるのかお悩みの方も多いと思います。その解決法として書いて伝える方法をお伝えします。まずは説明会を開催しますので、お気軽にご参加ください。
NPO法人日本インクルーシブ教育研究所では毎年、教室で活躍する学習・発達支援員を養成しています。一度、学習・発達支援員養成講座を受けただけでは多様な子ども達に合わせて適切なサポートをし続けることは難しいものです。そのため、ライセンス取得者だけでなく学習・発達支援員養成講座を受講したことのある方はどなたでも受講できるようフォローアップ研修も毎年開催しています。今回は講師に明蓬館高等学校校長 日野公三先生をお招きし、子ども達が中高生になるまでに必要なことについてお話しいただきます。

特定非営利活動法人 日本インクルーシブ教育研究所
Illustration by Naoko Ikeda
Logo design by Yukimi Nishimura